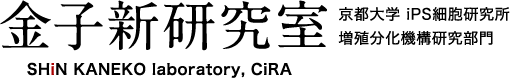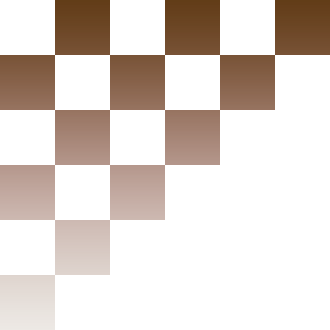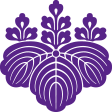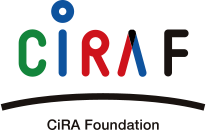著者:泉 響介 (京都大学大学院医学研究科脳外科学専攻)
著者:栗原 颯太 (京都大学大学院医学研究科医科学専攻)
指導:金子 新 (iPS細胞研究所副所長/教授)
指導補助:石川 晃大 (同金子新研究室 特定研究員)
金子研では、修士・博士学生の内から総説や論文を執筆することを推奨しています。
今回、博士課程在学中の泉さんと栗原さんに総説論文を執筆して頂きました。
学生の時分に論文を書いていくことについて、お話を伺いました。
今後、このページを御覧の皆様にとり、御参考になれば幸甚です。
著者:泉 響介 (博士課程3年生)
総説:ゲノム編集iPS細胞を用いたuniversal CAR-T/NK細胞のフロンティア
掲載:週刊 医学のあゆみ「CAR-T細胞療法の最前線」, 第288巻3号
ISBN:10.1186/s41232-024-00328-3
著者:栗原 颯太 (博士課程1年生)
総説:Genome editing iPSC to purposing enhancement of
induced CD8 Killer T cell function for regenerative immunotherapy.
掲載:Inflammation and Regeneration, 2024
DOI:10.1186/s41232-024-00328-3
| ーー | それでは、よろしくお願いします。 |
| 泉: | よろしくお願いします。 |
| 栗原: | よろしくお願いします。 |
| 石川: | よろしくお願いします。 |
| ーー | まず、それぞれの執筆された総説のポイントを教えて下さい。 |
| 泉: | 他家移植向けの技術に注目して頂ければと思います。金子研が、これまでoff-the-shelfを目指した基盤技術を提供し続けてきたということが伝わればいいなと。 |
| 栗原: | 医療応用可能なiPS細胞誘導キラーT細胞を作製する基盤技術について、金子研の研究成果を中心にまとめました。総説内で言及してませんが、これら技術は、現在臨床試験が既に走っているCAR-iPS-NK細胞製剤にも応用可能なものも多いので、そういう拡がりも感じながら読んで頂くと、より面白いかなぁと思います。 |
| ーー | 総説論文を書くに当たり、まず、何から始めましたか? |
| 泉: | ラボの研究の研究ですね。先輩方の研究をとにかく読みまくった。とても勉強になりました。今まで、金子研内の別グループの研究について全然理解出来ていなかったことに気付けました。知識のマージンがとても拡がりました。 |
| 栗原: | 論文自体、初めてでしたので、書き方も全然分かりませんでした(笑) なので、泉さん同様、金子研の論文を片っ端から読みました。引用欄から文献を孫引きし、業界の知識や論文の構成、書き方などを学びました。 |
| ーー | 総説を書く難しさ、大変だったことを教えて下さい |
| 泉: | 論文全体の流れを組立てるところと、表現方法です。理解を自分の言葉にした上で、載せる情報・表現を取捨選択していくのが、とても難しかった。例えば、最初、紹介する研究が実施した解析手法一つについても原理から説明しようとして、ボリュームが物凄く膨らんでしまったんです。そこで、この「総説」で本当に伝えるべき情報は何かを考え、読者側で補完可能なものの説明を削ぎ落していったのですが、この「何を残し、何を棄てるか」を選ぶのが、本当に難しかったです。 |
| 栗原: | 初体験だったので、全部大変だった、というのが正直なところでした!まとめた知識を文章(日本語)に落とし込んでいく作業も大変でしたが、英文を書きなれてなくて、英語表現を練る作業が本当に大変でした。石川先生に校正をお願いした後、専門業者に校正を依頼しましたが、都度返ってくる指摘内容で英文執筆を勉強していたという感が強いです。 |
| 石川: | 執筆補助での印象ですが、泉さんは論説文を書き慣れているが故に、説明が硬かった一方、未経験の栗原君は、とても口語的で、感覚や印象による説明が多かったですね。ここは本当に、人によって違うなと感じました。これらを直しつつ、学術的表現に仕上げていくのが、指導者として難しかった。栗原君は、英文化もあり、特に。英語ならではの文法・表現に対応する必要があったので、栗原君も相当勉強になったと思いますが、指導する側としても勉強になったと感じています。 |
| ーー | そうですよね、普段英論文を読み慣れていても、書くとなると話は別ですからね……。また、泉さんから論文の大筋を決めるところが大変という意見がありましたが、ロジックを構築すること、それを正確に表現すること、どちらも難しいですよね。 |
| 泉: | 難しかったです。自分の理解があやふやだと、適切に表現出来ない。そもそも「理解する」ことが難しかった。論文でわからないところは、テキストやムック本などで知識を埋めていく必要がありましたが、お蔭で、とても理解の幅が広がったことを実感しています。 |
| 栗原: | そっちも大変でした。とにかく、どういう風に論を展開していいものか、全然分からなかったので……。ベースとなるストーリーが決まるまでは凄く悩みました。大筋でも出来ると、「このトピックはここに入れよう」とか、指導の先生方と相談しながら進められたので若干安心感はありました。 |
| ーー | 自分で書いた総説を読み返してみて、どう感じましたか? |
| 泉: | まぁ、こんなもんかなと。私は和文総説だったので、栗原君ほど大変ではないですが、苦労に見合う出来だとは思います。特に、自分で作ったfigureには、凄く満足しています。カラーで入れて頂いて、amazonや書店に並んでいる「医学のあゆみ」で見た時は、何かの達成感を覚えました。 |
| 栗原: | まだ、こう書けばよかったとかっていうのはないですが、当初思ってたものよりもかなり文章が短いなと感じています。石川先生とチェックしながら、ブラッシュアップを続けていく中で、同じ情報量で文章がスッキリ短くなることに感動しました!今、読み返すと、本当に最初の文章量に比べて凄くスッキリ短くまとまっているなと自画自賛してます(笑) |
| ーー | 総説を書いてみてよかったですか? |
| 泉: | よかったです。知識のアウトプットって大事なんだなと。また、論文投稿で必要な、金子先生や出版社とのやり取りも重要な経験でした。自分の書いた文章が残るのだということ。医学のあゆみは書店に並ぶので、何か、やってやったぞという自信は出来た。これは今後のキャリアで確実にプラスになります。そして、この世に残り続けるものを出したことで、家族も喜んでいます(笑) |
| 栗原: | よかったです!絶対に、博士論文を書くときに参考にもなると思いますし、博士論文投稿から逆算して動くイメージにも繋がりました。 |
| ーー | 総説を書き始める時点の自分にアドバイスするなら? |
| 泉: | やっぱり、他のグループのprogress reportにも、もっとちゃんと興味を持って臨み、ちゃんと基礎的な理解が追い付く程度には自分以外の研究についても勉強しておいた方がいいぞと。普段のprogress reportに参加している自分の真剣さが足りていなかったということを痛感しました。 |
| 栗原: | とにかく、早く取り掛かれよと。書始めまでの下調べが本当に大変で……。Original articleだと、自分のデータを集めてストーリー作るとこ?本当に、取り掛かるまでの心理的ブレーキが凄かったです。書き始めると、先生方と話ながら進められるんですけど、ベースのストーリーは自分でどうにかしないとなので。特に、僕の場合は、モタモタしているうちに修論とか再生医療学会の発表準備とかも重なってきてしまって、それはもうタイヘンで。だから、もう、とにかく早く情報をまとめて、早く取り掛かれ!って思います。 |
| ーー | 石川さんは、博士学生が総説を書くことについて、どう感じましたか? |
| 石川: | それは、絶対的に良かったと感じています。まず、理解するということは、伝えることが出来るということ。入って1年2年くらいの学生は、普段の議論や教育の中で、何となく聞き流し、わからないまま放置するということが多いかと思います。学生自身が、それに気付き、修正することができたのはよかった。また、早いうちに、論文のパブリッシュに到るまでの流れを具体的に経験できたというのも、非常に大きい。そうすると、いざ、博士論文発表の段になった時に、スムーズに動き出せると思う。実験計画を俯瞰してみることも、終点を定めて見るなら見方も組み方も変わると思いますね。最後に、就職するにせよ、アカデミアに残るにせよ、実績が必要。自分自身、学生時代の実績には苦労していますし。総説執筆経験で自信もつくし、実績があれば変な焦りを感じることなく、研究の場に出ていくことが出来るかなと思います。 但しー一執筆補助1人につき1総説が限界。2つ同時は死ねる。 |
| ーー | 皆さん、ありがとう御座いました。最後に、この執筆で学んだことのうち、今後の研究に生かしていけることを教えて下さい。 |
| 泉: | 総説の知見ではないですが、やはり、論文を出すという作業を一通り経験できたことは非常に大きい。日本語でさえ、こんなに大変なのか。今回、一次体験としてそれを経験したので、今後、博士論文を書いていくこと、その先のキャリアを続ける中で、必要な作業感覚・時間感覚を得られたと思っています。 |
| 栗原: | 僕自身、今は臨床寄りの研究に携わっているのですが、この総説執筆で臨床ベースの研究が、あらゆる基礎研究の上にあるということを実感しました。今後は、今の研究を進めながら、基礎的な知見をどの様に応用すれば、より良い製剤が出来るかなどと考えていきたいと思います。 |
| 全員: | ありがとう御座いました。 |